宅建士試験は世間では初歩的な資格試験だといわれています。
しかし、受験した方はわかると思いますが、決して簡単に合格できる試験ではありません。
合格率に惑わされないでください。
すでに、15年以上前の宅建士試験とは別物です。
今回は、宅建士試験が難しい理由について説明します。
客観的な理由と、受験者としての主観的な理由を述べてみたいと思います。
理由その1: 合格基準点が高い
宅建士試験の合格点は、31点から38点とばらつきがあります。
特に近年では、七割以上の正答率が要求されています。
宅建の合格率は17パーセント前後ですから、高得点を取らないと合格圏に入れません。
冷静に考えてみれば分かりますが、
仮に宅建士試験が簡単に取れる試験だとすれば、合格点は50~60パーセント付近になるはずです。
理由その2: 試験問題が難しい
宅建試験は、権利関係、法令上の制限、税その他、宅建業法、5問免除問題、という5個のカテゴリーから成ります。
この中で、権利関係(民法)が特に新規問題が多くなり、過去問の繰り返しだけでは対応できません。
権利関係だけでも14問も出題されますから、この分野を捨てることはできません。
また、全体的にひっかけ問題が多く、権利関係以外でも難問が出題されることもあります。
例えば、みなさんブレースってわかりますか?
正解は木造建築の柱と梁の間に入れる筋交いのことです。
この問題が令和7年の建物に関する問題(5問免除うちのひとつ)として出題されました。
このような、ハメ問題や難問をこなしつつ、七割以上の得点を取る必要があるのです。
理由その3: 確実に合格点を取ることが難しい
これは、先ほど述べた「問題が難しい」という特徴に関連するのですが、
宅建試験では難問であっても、実力のある人であれば「二択までは絞ることができる」問題が結構多いです。
これらの問題を正解できるか否かが、合否を分けます。
つまり、「運の要素」がからんできます。
仮に2人の受験者がいたとして、とある試験で「A君は33点、B君は40点とれたが、別の試験では逆の結果になった」
という現象が起こりえます。
合格ライン付近の人達は、合格、不合格のいずれに転んでもおかしくないということです。
要するに、確実に合格できるような実力をつけるためには膨大な時間が必要になります。
一方で、合格ライン付近のレベルまでは、多くの方が400時間程度の勉強時間で到達可能です。
ちなみに、宅建士試験の合格者の中で一発合格者は半分程度です。
理由その4: 受験者のレベルが上がっている
宅建士試験の合格率は17パーセント前後で、受験者数は20万人前後です。
この傾向は昔からたいして変わっていません。
しかし、宅建士試験の合格基準点は近年では高止まりしています。
これは何をあらわしているのでしょうか?
推測ですが、受験者のレベルは年々上がる傾向にあると考えられます。
大昔に宅建士に合格した人は、一発逆転を狙った方も多かったのはないでしょうか。
近年では不動産会社も大卒を雇うようになり、学習習慣を備えた人材が増えています。
行政書士や司法書士に比べて簡単なのか?
宅建とよく比較されるのが行政書士や司法書士などの法律系資格です。
一般に、行政書士は1000時間、司法書士は2000時間から3000時間が合格までに必要な期間だとされています。
宅建の場合、初学者の場合は約500時間程度で合格レベルに達するとされています。
ところで、学習時間と難易度は同じものしょうか?
クリアするまで長時間を要するゲームと、短時間でクリアできるゲームの難易度は?
そうです。学習時間と資格試験の難易度は、それほど関係がないのです。
そして、受験者層のレベルは同じでしょうか?
合格者の平均年齢も大分違います。
宅建士試験は35歳前後、そして行政書士と司法書士は40歳以上です。
一般に、資格試験では若い方が有利です。
司法書士試験は難関試験とされており、学歴も比較的高い層が受験します。
しかし、決して受験者は若い年齢が中心ではありません。
つまり、宅建と行政書士、司法書士等の試験難易度を比較すること自体が難しいのです。
まとめ
今回は宅建士試験が難しい理由について説明しました。
宅建士試験は年々難化傾向にあるので、はやめに試験を受けることをおすすめします。

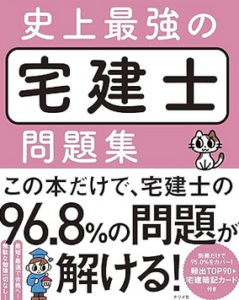
コメント